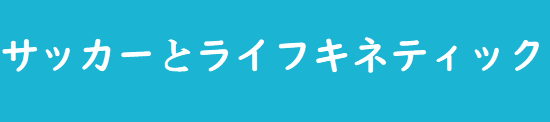今回は、”サッカーにおけるディフェンス能力を向上させる要素およびコツ“、そして”その秘訣でもある学習転移とカンナバーロ“についてお伝えしていきます。
私のスクールは、約10年前から日本全国の方を対象にムービーレッスンという形式で活動をしてきました。
その中で、”不思議とディフェンスでレギュラーになる選手が多い“ので、そこには何かしらの要因があるのではないかと思い、今回そのことついて書こうと思いました。
何故、サッカーの技術やコーディネーション能力を高めていく中で”ディフェンス能力がアップ“したのでしょうか?
そのことについて、少しでも皆さんのヒントになればと思います。
目次
①ディフェンスが上手くなる為に

私の方では、特に”ディフェンスが上手くなる為のトレーニング“を提供しているわけではないのですが、”ディフェンスとしてレギュラーを掴み取る選手“が頻繁に出てきています。
どの位の頻度で出てくるのかは定かではありませんが、当スクールでサッカーの技術やコーディネーションが習得できた選手が、これまでに”全国大会でセンターバックとして出場“したり、”Jクラブの下部組織の1軍でセンターバックとして公式戦に出場“したりしています。
当初、これは単なる偶然なのかなと思っていましたが、”サッカーの技術とコーディネーション“を習得し、更にその”原理を知った“ことで、ディフェンスをする上で”それらの能力を役立てることができるようになった“と考えて良いと思います。
つまり、
冒頭でお伝えした”学習転移が起こった“
ようなのです。
他のスポーツに移行することだけが”学習転移“ではなく、同じ競技の中で各ポジションがあるわけですから、”それまでに培った技術や能力をそのポジションで活かせる可能性もある“わけです。
例えば、”サッカー日本代表のセンターバック昌子選手“は、”育成年代ではオフェンスをしていた“という過去があり、彼の能力を最大限に活かす為に”指導者がセンターバックとして起用“し、それによって”彼の能力が開花“しました。
過去の日本代表選手を見てみると、”柱谷哲二氏“や”ゴン中山(中山雅史)氏“も”育成年代でオフェンスとディフェンスを掛け持ちしていた“という過去があります。
他にもあげたらキリがありませんが、このように逆の立場になって(攻撃と守備が入れ替わって)も、”今まで得た技術や能力を活かせる“ことがあります。
ちなみに、国立市で活動しているサッカースクール(ライフキネティック・コース)に参加している選手の中で、”ネイマールが好きだ!“と言っている子がおりますが...
今年(2019年)の春から新チームに移籍し、すぐにさま”センターバックとしてレギュラーの座を奪うことに成功“しました。
当初、ライフキネティック教室に参加されていた際、”左右の脳を同時に使う“ことや”コーディネーション能力“に少し課題もありましたが...
約2カ月ほど活動して、こうした”能力を向上する“ことができ、現在は更に良い感じで”サッカーの技術とコーディネーション能力を瞬時に出すことができる“ようになってきています。
ようするに、”ワーキングメモリーを向上“させると、ある分野において”器用な人間“になれるのだと思います。
そういう私も、小学生の低学年ではディフェンスをやらされ、高学年ではウィングのポジションで起用され、高校ではツートップをやったり、2軍のコーチからトップ下で起用された時期があります。
更に社会人の県リーグでは、”全国レベルの基礎技術と基礎能力を習得していた“こともあり、高い守備能力とスタミナがかわれて、”守備的なミッドフィルダーとしてレギュラーとして出場“していました。
また、市の地域リーグに所属していた頃は、チームの失点を減らす為にと”自らの意思でセンターバックとしても出場“していました。
このように、”ワーキングメモリーを向上“させることができると、”どの分野でもそれなりに活躍することができる可能性が高くなる“ようです。
ですから、育成年代のサッカーでは、そのポジションに固執または極めようとするのではなく、”サッカーに必要な基本技術と基本のコーディネーションを習得することが重要“だということが分かります。
ちなみに私の場合は、当時ライフキネティックなどありませんでしたから、学校が終わってから公園などの”屋外で上級生たちと遊んだ“ことによって、ワーキングメモリーを向上させることができたと思います。
他にも、”スイミングスクール“や”公文式(塾)“にも通っていたので、”それらも少なからず影響を与えた“と思います。
なので個人的には、”サッカーのディフェンスが上手くなる為の方法“として、”サッカーに必要な基礎技術と基礎的なコーディネーションをしっかりと育成年代から学んでおくことを推奨“します。
この2つの要素を学び、理解し、運動スキルを習得できたからこそ、”学習転移を起こすことができた“わけで、”様々なポジションでその技能を活かすことが可能になった“のだと思います。
そして、その中で”自分のストロングポイント(強み)を発揮することができるポジション“を見つけられれば、更にサッカーの試合で活躍できるはずです。
②ディフェンスには予測する能力が必要

サッカーのオフェンスとは違って、”ディフェンスには相手のプレーを事前に予測する能力“が必要です。
でも、先ほど伝えたサッカーの基礎技術や基礎的なコーディネーションを知らない、または習得していなれば、相手オフェンスの選手が”どのような動きやプレーをするのか予測する“ことができません。
私も守備的なミッドフィルダーやセンターバックをやる時に感じるのですが、”自分の経験から、次はこの辺を狙ってくるだろう“と予め予測することができます。
こうした経験を増やしていくことで、逆にオフェンスをした際に”こういうプレーをするとディフェンスは嫌だな“というのが分かってきます。
そして、”どのように動けば相手は反応しにくいのか?“や”相手にとって嫌なプレーなのかが逆の立場として分かってくる“というケースが頻繁に出てくるようになります。
当然、その動きや嫌なプレーを逆の立場で同時に知ることができるわけですから、それによって”相乗効果が期待できる“といった利点もあります。
しかし、あまりにも”予測が速すぎるのも問題“になる時があります。
ちなみに、少し話が難しくなってしまいますが、”運動生理学という分野“があり、人間がついつい無意識にやってしまう”予測の仕方(癖)“というものが存在します。
これは、オフェンスであってもディフェンスであっても、無意識のうちにやってしまうことがあり、”その存在を知っているかどうか“で、”自身のプレーに違いが出る“ようになります。
例えば、”メッシが何故あれほどドリブルで相手ディフェンスを抜き去ることができるのか?“とか、”元イタリア代表カンナバーロは何故あれほどボールを奪うディフェンスができるのか?“など、こうしたことが次第に分かるようになります。
相手が素早く予測(判断)すれば、それに従って”身体を動かす為の準備“や”実際の動き出しも速くなっていく“ので、この”予測(判断)の速さ“によって、逆に”判断を誤ってしまう“という場面も頻繁に出てきます。
例えば、
昔からの遊びで”あっち向いてホイ“という遊びがありますよね?
これは、ジャンケンをした後に、相手の顔を指差す遊びですが、これを更に発展させたのが、”叩いて被ってジャンケンポン“といった芸人さんたちがやるモノでしょうか(笑)
これを見ていると、分かっていてもついついやってしまう芸人さんたちの動きに、我々は面白おかしくなって、ついついテレビに見入ってしまいますよね?
これをサッカーの1対1で考えてみると、”相手をドリブルでかわせるタイミングだったのに、その時にかわす動きができなかった“とか、”相手に素早く反応できたのに、その時にボールを奪えなかった“という人間の持つ運動生理学が徐々に分かるようになっていきます。
この辺については、私が独自に伝えている”フィードフォワード理論“で詳細を明らかにしていますので、興味がある方は”ムービーレッスンのフルサポートをご活用“ください。
このように人間には
“分かっていてもついついやってしまう生理的な動き“
というものが存在します。
それを見事に運動プログラムに作り上げたのが、ライフキネティックなのではないでしょうか。
咄嗟に”右脳と左脳を同時に使い分ける場面“や”瞬時にその場で表現しなければならない運動スキル“など...
当然、これらを”脳が素早く判断“できなければ、それを”実現するのが難しいのは目に見えている“はずです。
ですから、”その動きやプレーをしっかりと見極めること“ができて、”よりベストなタイミングでそれを実行に移せるか“が重要になってきます。
オフェンスとディフェンスは、ある意味、表裏一体です。
ただ闇雲に
“予測する能力を高めれば良い“
ということではありません。
“サッカーのディフェンス“では、
“どのような時に、どのような動きができて、どのような動きができないのか?“
そして、
“どのようなタイミングの時に、どのようなコーディネートができて、どのようなコーディネートができないのか?“
を知ることが大切です。
③最後まで粘る技術と能力が必要

サッカーのディフェンスでは、”最後まで粘る技術と能力が必要“です。
この”最後まで粘る技術と能力”ですが、
皆さんはどのように考えますか?
私の場合は、
“自分の足を止めずに相手オフェンスに食らいつく“
というイメージが頭に思い浮かびます。
私が高校時代、ドイツとオランダで学んだことは、”ボールを奪えると判断できた時だけ、身体を投げ出したスライディングタックルをしても良い“と、現地のコーチから教わりました。
そうすることで、ボールを一時的にコートの外に出してアウトオブプレーにすることで、その間に守備陣形を整えたり、立て直したりする時間を作ることができるからです。
これは”サッカーの守備(ディフェンス)の基本“であり、強豪ドイツも自国のサッカーのレベルを押し上げていく為に、”守備(ディフェンス)の基本徹底“を育成年代から行ってきました。
でも、これだけではディフェンスは上手くなりませんよね。
私が多くの子供や選手たちを見てきた中で、
ディフェンスでは、”3つのプレーに分類できる“と考えています。
1.ボールが奪えると思って足を出してしまう
1つ目
“ボールを奪えると思って足を出してしまう“
これは多くの育成年代で見られるパターンでもあります。
このプレーをしてしまうことで、”片方の足に重心が乗ってしまう“ことで、”それによって逆側にターンされたり、ボールを切り返されてかわされてしまう“といった場面が出てきてしまいます。
酷い選手だと、
“クルッと身体を入れ替えられて、あっさりと抜かれて置き去り“
にされてしまいます。
この辺については、身体と力の伝え方や使い方も関係してきますが、今回これに関しては、あえて触れないでおくことにします。
2. 両足で地面を滑るようにストップしてしまう
2つ目
“両足で地面を滑るようにストップしてしまう“
これも育成年代で多く見られるプレーの1つで、とくに土や砂、”滑りやすい屋内(体育館)のようなコートで頻繁に見らる動き“です。
これをしてしまうと、両足が地面に接地されたまま、地面の上を滑ってしまっている為、”次の反応や動きをする為に素早く動き出す“ということができなってしまいます。
また、これは”ディフェンスが疲れてくると見られる現象“でもあります。
3.しっかり最後まで足を動かして追いかける
3つ目
“しっかり最後まで足を動かして追いかける“
これができている育成年代の選手は、あまり多くありません。
何故なら、育成年代でディフェンスをしている選手の多くが、”フィジカル重視で足の速さや身体の大きさで有利になっているだけ“だからです。
育成年代でフィジカルが優れていると、ちょっと走れば追いついてしましますし、ちょっと足を伸ばせば届いてしまう為、最後まで足を動かさなくてもボールを奪えてしまうというのが、”日本国内の育成年代におけるディフェンスの現状“のように感じます。
先ほど私がお伝えした”元イタリア代表カンナバーロ“は、この”最後まで足を動かすということが唯一できていた選手“であり、ボールを奪うタイミングもベストでした。
彼は、2006年ワールドカップ(ドイツ大会)でイタリアを優勝に導き、当年のバロンドールで欧州年間最優秀選手賞を受賞。
UEFAベストイレブンおよびFIFA最優秀選手賞にも選ばれています。
それでは彼のディフェンスを動画でご覧になってみてください。
(一部省略していますので約40秒の動画です)
この動画を見た時、”ドイツ・オランダで現地のコーチに教わった基本ディフェンスの大切さ“を改めて感じさせられました。
ボールを奪う際の身体を投げ出すスライディングでは、”ボールをコートの外に出して、一時的にゲームを中断“させています。
更に、”最後まで足を動かし“て、”相手がコントロールしたボールにも反応“できています。
ペナルティ付近でスライディングをして自身が倒れてしまった場合でも、上手く自分の手を使いながら身体を浮かせるなどして、”最後まで粘って反応“していますね。
ディフェンスをする上で重要なことは、スライディングをしてしまうと、その場から選手が1人消えてしまうことになるという点です。
これは
“サッカーの基本的な考え方によって導き出された最も確実な理論“
です。
守備をする上で数的不利にならない為に、
“相手を遅らせて時間を稼ぎ、守備ができる人数を確保“
しなければなりません。
そして、
“ディフェンスをする味方選手が多い方にオフェンス選手を追い込む“
こと。
相手の素早いカウンター等では、
“(必ずボールを奪えると判断できれば)コートの外にボールを出して、守備の陣形を整える、または立て直す時間を作る“
こと。
相手からボールを奪った後も、
“素早く攻撃へ移れるように、ゴールまでの最短コースにパスを送り出す“
こと。
先ほどご紹介した動画では、上記要素が”カンナバーロのプレーにしっかりとあらわれている“のが確認できると思います。
それにしても、カンナバーロのボールを奪えると判断した時のボールに向かっていくスピードは流石です。
これぞまさしく”世界最高峰のディフェンス“と言えるでしょう。
まとめ
いかがだったでしょうか?
今回は、”サッカーにおけるディフェンス能力を向上させる要素およびコツ“、そして”その秘訣でもある学習転移とカンナバーロ“についてお伝えさせていただきました。
何故かサッカーでは、不思議と”攻撃選手が守備のポジションに変わる“ことや、”守備選手が攻撃のポジションに変わる“ことがあります。
特に、センターバックとセンターフォワードの入れ替わりは、私がサッカーを経験してきた中で”最も多かった出来事“でした。
フォワードの選手というのは、どうすればディフェンスの嫌なプレーができるかを知っており、逆にディフェンスの選手というのは、フォワードの嫌なプレーを身をもって体験しています。
つまり、互いにそれらを学習し、それが”学習転移“となって別ポジションとなった時に、”過去に培った能力を活かせる“ということがあります。
そう考えた時に、
“学習転移によって違ったポジションで能力が開花する“
なんてことが起こるかもしれませんね♪
例えば、
フィーゴやベイルやピルロといった世界トップレベルの選手たち...
こうした選手たちも、ある時に”別のポジションにコンバート“したことで、”自分の能力を開花させた“という事例もあります。
学習転移を正のものにするのか、負のものにするのか...
全ては、
“これからの自分の行動次第“
なのではないでしょうか?
ここまでお読みくださり、ありがとうございました♪