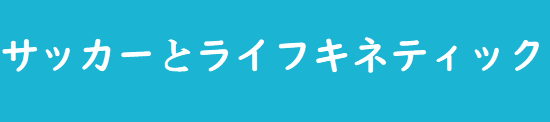今回は、”少年サッカーの練習メニューについて“と、”低学年と高学年で知っておくべきポイント“を、いつものようにライフキネティック・トレーナーの視点からお伝えさせていただきます。
現在では、様々なサッカースクールが存在している為、”幼児からサッカーを始める子“もいれば、”小学生からサッカーを始める子“もいます。
ですが、今回は”小学生からサッカーを始める時“に、”より効果的な練習メニューとはどのようなものなのか?“を年代別にお伝えしていこうと思います。
各年代において、細かくお伝えするのも良いのですが...
この記事では、あえて”低学年“と”高学年“の2つに分類し、その年代に”一番適した練習メニュー“というものをライフキネティック・トレーナーの視点から説明していきます。
なお、過去に”少年サッカー“に関する記事を幾つか書いていますので、参考までに下記の記事にも目を通していただけたらと思います。
それでは、次のコーナーから”少年サッカーの練習メニュー“と”低学年および高学年の練習メニュー“についてお伝えします!
目次
①少年サッカーの練習メニューについて

まず、”少年サッカーの練習メニュー“についてですが、小学生をメインに考えた場合に、”低学年と高学年の2つに分類“することができます。
では、この2つに分類した”サッカーの特徴“を下記に書き出してみます。
【低学年】
- ほとんど周囲の状況を見ずに、ボールのみ固視する傾向がある
- 選手がボールに集中して群がる性質がある
- ポジションを意識したプレーがほとんどできない
- 戦術を理解することが困難
- フィジカルで優れている選手の多いチームが試合に勝ちやすい
【高学年】
- 学年を重ねるごとに、周囲の状況を把握できるようになる
- ボールだけでなく、敵・味方・ゴール等も見られるようになる
- ポジションを意識したプレーを選択できるようになる
- 少しずつ戦術的な理解も高まっていく
- チームやクラブの特徴によって、試合の勝敗が左右されやすくなる
このような感じで、”少年サッカーの低学年と高学年“とでは、”様々な能力に著しく差が見られる“傾向があります。
そして、この”様々な能力差“が、脳神経可塑性で言われている”学習の個人差“だと言われています。
なお、”学習の個人差“に関しても過去に幾つか記事を書いていますので、こちらにも目を通していただくと、更に理解が深まると思います。
このような特徴がある中で、
“低学年と高学年“とでは
どのような練習メニューを考えるべきなのでしょうか?
②低学年の練習メニュー

では、先ほどお伝えした”低学年のサッカーの特徴“を踏まえた上で、この年代に”最も適したトレーニング(練習)メニュー“を考えてみたいと思います。
念のため、もう一度この年代におけるサッカーの特徴を載せておきます。
- ほとんど周囲の状況を見ずに、ボールのみ固視する傾向がある
- 選手がボールに集中して群がる性質がある
- ポジションを意識したプレーがほとんどできない
- 戦術を理解することが困難
- フィジカルで優れている選手の多いチームが試合に勝ちやすい
1.ボールのみ固視する傾向がある
この年代は、”周囲の状況を把握する能力“よりも”1つの部分に集中する傾向がある“ようです。
つまりそれが、
“ボールのみ固視する“
という部分です。
よく天才と言わているサッカー少年たちは、この部分でかなり同年代に差をつけており、ボールだけでなく、同時に”周囲の状況も把握することができる“ようです。
では参考までに、幼い頃の”中井卓大選手“のプレーを動画で見てみましょう。
(一部省略していますので、約40秒の動画です)
ただ、目の前の相手選手をドリブルでかわしているわけではないのがハッキリと分かりますよね(汗)
しっかりと、”周囲の空いたスペースも見えて“おり、”相手選手のいない位置へボールを運ぶ“こともできています。
これだけの能力があれば、足元の技術を習得すればするほど、その効果がサッカーの試合で活かされるはずです。
こちらの”周囲の状況を把握“についても、過去に記事を幾つか書かせていただいておりますので、是非こちらにも目を通してください。
ここで、多くの親御さんや指導者が悩むところは、”技術を身につけさせるのが先か“それとも”状況判断を身につけさせるのが先か“という点ではないでしょうか?
この辺についても、徐々に次のコーナーでお伝えしていきますので、是非最後まで記事をお読みになってください。
2.ボールに群がる
先ほどの”中井卓大選手の動画“を見ても分かるように、彼のボールを奪おうと”相手選手がボールに群がっている“のが確認できると思います。
このように、この年代では”チーム(グループ)として守備をする“ということができないことから、このような”団子サッカー”になってしまいます。
よく、低学年同士のサッカーの試合を見ていると、フィジカルに優れていたり、戦術に優れているチームの方が得点を多くあげ、試合に勝利するという場面を見かけます。
しかし私(保護者としても指導者としても)の経験上、しっかりとこの年代で”身につけるべきサッカーの基本技術を習得しているチーム“が、高学年になった時に”試合内容で大きな差をつけて勝利“しています。
これらのことから分かったことは...
それぞれ指導者が持つ指導プラン次第で、
“個々の能力が大きく変化する“
ということです。
以前、神奈川の県ベスト4に入れるレベルのジュニア(低学年)同士の試合を何チームか観戦したことがありますが、どちらかというと”技術よりも戦術重視のサッカー“をしていたように、私は個人的に感じました。
当然、
“過去に久保建英選手も所属していた某クラブ“
も観戦しています。
ちなみに、どこのクラブの指導が良い悪いということではなくて、この時に”それぞれのクラブによって指導方針が全く違っている“というのを感じることができました。
なお、この大会でJクラブ下部組織は1チームも参加していませんので、”神奈川サッカーのレベルの高さを身をもって痛感“しました(汗)
3.ポジションを意識したプレーができない
当然ながら、この年代ではボールばかりに気を取られているわけですから、”ポジションを意識したプレーができない“というのがほとんどです。
それでも、”指導者がこれらをしっかりと意識“していれば、”低学年からでもボール(パス)を繋ぐサッカーを指導“するはずです。
ここで、注意してほしい点ですが...
日本サッカーの育成年代では、”技術を優先した指導“と”戦術を優先した指導“といった感じで、大きく2つに分類できるように思います。
しかし海外の指導者は、
“この2つのちょうど中間を意識したサッカーの育成(指導)“
をしています。
以前、某私立高校のサッカー部を指導していた際に、”スペインの強豪クラブでスクールコーチをしていた方“と、”サッカーの育成“について個人的にメールを交わしたことがあります。
その際、”日本ではサッカーの普及活動と育成活動が入り混じっている“とアドバイスを受けたことがあります。
では、皆さんのお子さんたちが所属するクラブやチームでは、指導者が”どのような指導方針“を持ち、”選手たちを指導“しているでしょうか?
是非、一度ゆっくりと考えてみてください。
4.戦術を理解することが難しい
先ほどのコーナーで、”技術優先か戦術優先か“という話をしましたが、”海外にの育成では、どちらも重要というのが一般的(常識)“のようです。
それでも、現在の日本サッカーのジュニア年代のように、指導方針がどちらか一方に片寄ってしまうのは、日本サッカー独自の指導法がいまだに見つかっていないからではないかと思います。
また、一部の指導者の中には、”幼い子供たちがそれほど高度な戦術を理解することなどできるはずがない“と思っている方もいるでしょうし、”ジュニアでは戦術よりも技術の方が大切!“と考える方もいると思います。
こうした背景には、”幼いうちは戦術を理解するのが難しい年代だから...“という”日本人が勝手に持っている固定概念がある“ようです。
しかし、とあるスペイン人の指導者が日本に訪れた際に、日本人の指導者が”幼い頃から戦術を指導すべきなのか?“と質問をしたところ、このスペイン人の指導者から”では何故、幼い頃から戦術を指導しないのか?“と逆に質問をされたそうです。
しかしこの時、質問を投げかけた日本人の指導者は、その質問に対して”最もな意見や理論を述べることができなかった“とのこと。
このように、日本人指導者の多くは”これといった理論を持たず“に、”他国のサッカーの良い部分やノウハウだけを取り入れる傾向がある“ようです。
ちなみに、私自身は”海外の指導方針を好んで選択“します。
何故なら、
“全てにおいて(技術も能力も)不器用なサッカー選手を育てたくない“
からです。
その為、私にとっては”ライフキネティックという運動プログラムが必要不可欠な存在“でした。
なお、ライフキネティックは”脳の神経可塑性“を上手く活用した全く新しい運動プログラムであり、この運動プログラムとの出会いによって、私の悩みや疑問が一気に解消されました。
まだ、”ライフキネティックおよび脳の神経可塑性“についてご存知のない方は、下記の記事に目を通して更に理解を深めていただければ、この先の内容がより把握しやすくなると思います。
5. フィジカルで優れている方が有利
こうしたことから、”低学年のサッカー“では”フィジカルに優れている方が圧倒的に有利となることが多い“ようです。
特に、”1人でもトップに足の速い選手“がいれば、ボールを縦に蹴り出し、それを追いかけてゴールをするだけで勝ててしまう試合が山ほど出てきます。
しかしですね...
これには”大きな落とし穴“があります。
私も息子のジュニアサッカーを幼い頃から見てきましたが、茨城県内の某Jクラブ下部組織には、隣接した県外の地域から、優秀なフィジカルを持った選手が集まってきます。
私の周囲にある地域で、かなり足が速いと評判だったとしても、こうした”プロクラブの下部組織に所属している選手たちの方が足が速い“というのが現状です。
これまでにも、日本国内で最速と言われた日本人サッカー選手が何人も海外に挑戦していますが、彼らはバルセロナにもレアルマドリードにも所属することができていません。
それよりも、”久保建英選手“や”安部裕葵選手“のような”周囲の状況を素早く把握する能力が秀でている選手“を”海外の強豪クラブは好んで獲得する“ようです。
これまでは、”技術が高ければ海外で活躍できる“とされていたものが、”技術は当たり前で、それに加えて判断能力も必須“とされてきています。
ですから、いまだに”どちらか一方の指導方針で指導を受けているだけ“では、”海外で通用するようなサッカー選手には育たない“かもしれないのです。
なお、”久保建英選手や安部裕葵選手“に関する記事も、過去に書かせていただいておりますので、是非こちらにも目を通していただけたらと思います。
こうしたことから、”低学年の最も適した練習メニュー“は、”技術と戦術および判断力を組み合わせたバランスの取れたトレーニングが必要“とされます。
現在、こちらのスクールでは
“技術・戦術・判断力のバランスが取れたトレーニングを作成中“
です。
完成しましたら、是非こちらのブログでも少しずつ皆さんに公開していきたいと思います♪
では、次のコーナーからは、”高学年の練習メニュー“について考えていきたいと思います。
③高学年の練習メニュー

それでは、ここから”高学年の練習メニュー“についてとお伝えしたいと思います。
再度、この年代におけるサッカーの特徴を載せておきます。
- 学年を重ねるごとに、周囲の状況を把握できるようになる
- ボールだけでなく、敵・味方・ゴール等も見られるようになる
- ポジションを意識したプレーを選択できるようになる
- 少しずつ戦術的な理解も高まっていく
- チームやクラブの特徴によって、試合の勝敗が左右されやすくなる
1.周囲の状況を把握できるようになる
この年代になってくると、徐々に年代を重ねていくことで”周囲の状況を把握できるようになる“傾向が強くなり、徐々に”組織的なサッカーができる“ようになっていきます。
ただし、”指導者に怒鳴られる(叱られる)“からそうなっているのか、それとも、”個々の能力が向上して個人が判断“してそうなっているのかは、かなり判断に迷う部分でもあります。
できることなら、
“後者の方がベスト“
ですよね(汗)
では、何故スペインなどの”海外のサッカー強豪国は、こうした周囲の状況を把握する(判断する)能力が高い“のでしょうか?
その要因は、
“サッカーの指導方針(または育成システム)が根本的に違っている“
からだと思います。
例えば、サッカー強豪国では”自国でワールドカップやオリンピック開催が決定する“と、”国をあげてサッカーの育成システムを強化する“というのが当たり前です。
しかし、日本はどうでしょうか?
残念ながら、日本サッカー協会が奮起しているだけで、”国をあげてサッカーを後押しするといった状況にならない“というのが現在の日本サッカーの現状です。
その為、多くのサッカー指導者は”休日にボランティア(無給)で選手たちを指導するのが当たり前“のようになっています。
また、多くの指導者はほとんどが無給だというのに、”サッカーの指導者ライセンス“や”審判の資格“を取得することが必要不可欠と言われています。
こうなってくると、”ボランティアなのだから我々に自由な指導をさせろ!“となってしまうのが目に見えて分かります。
当然、こうした指導が地域に増えていくと、”サッカーの育成(内容)を重視する指導よりも、試合の結果を重視する指導が多くなっていく“はずです。
正直、この曖昧な状態のシステムでは、”指導者が試合に勝ちたいのか?“、それとも”選手たち自身が試合に勝ちたいのか?“がハッキリしませんよね...
私は個人的に、”こうした「ごちゃ混ぜの指導」が嫌い“なので、例え選手たちに能力差があろうとも、サッカーの普及ではなく、サッカーの育成を意識した指導(トレーニングの提供)を徹底するように心がけています。
ただ、私自身だけがサッカーの育成を意識しても選手たちの判断力などは向上しませんので、”選手たち自身が意識できるようなトレーニングや声掛けアドバイスをする“ように、自分なりに様々な工夫をしています。
なお、サッカーのトレーニングで”子供(選手)たちの集中力が激変した効果“を記事にしましたので、是非こちらも参考にしていただけたらと思います。
2. 敵・味方・ゴール等も見られるようになる
当然ながら、この年代では”周囲の状況を把握する能力が高くなっていく“のですから、それに伴って様々なプレーをしながらボールだけでなく”敵・味方・ゴール等も見られる“ようになっていきます。
ちなみに、ここで1つキーポイントをお伝えしておきます。
ここでの”見る“という行動についてですが、
“見える“と”見られる“
では意味合いがかなり異なってきます。
1.(視界内にあるものの刺激で)目に感ぜられる。目にうつる。
2.見ることができる。視覚が働く。
つまり、”見える“というのは、
“個々によって能力に差がある“といったニュアンスがあるのに対し、
“見られる“は、見える能力はあるものの、
“個々にその能力を使うだけの条件が整っているか“
といったニュアンスがあります。
ですから、高学年になると低学年よりも”見られる“ようにはなるものの、その能力が、しっかりと”見える能力“になっているかどうかの判断が、”サッカーの指導をする者にとって必須項目“となります。
ちなみに、先週の国立市で開催したサッカースクールでは、複数の選手(4人)でグループになり、パス交換をするトレーニングを行いました。
選手たちは、それなりにボールをコントロールしながら相手選手を見られるようにはなっていますが、”ボールを受けるタイミング“や”パスを出すタイミングが見えていない“のを強く感じました。
それぞれ選手たちには、対象物が視界に入っているものの、何故か相手とのタイミングがズレてしまう場面を頻繁に見かけます。
ようするにこれが、
“視界に入るものは見られるが、確実に見える能力は備わっていない“
ということを意味しています。
そこで私は、パス交換をしている選手たち個々に寄り添いながら、”しっかりと相手の状況を観察“し、”ボールを受ける&ボールを出す“ように声掛けおよびアドバイスをしました。
すると、数分も経たないうちに、”選手たちはそれらを意識してパス交換ができる“ようになっていきます。
このトレーニングの前段階には、ライフキネティックを活用した”コーディネーション能力を向上させるエクササイズ“と”見る能力を向上させるエクササイズ“も行っています。
このように、ライフキネティックの理論を知ったことで、選手たちが”何故しっかりと見るということができないのか?“を知ることができるようになりました。
こちらの”見る“についても、過去に記事を書かせていただいておりますので、是非参考にしていただけたらと思います。
こうしたことから、ハッキリと分かってきたことがあります。
それは...
それぞれ選手たちには、それをこなせる能力が備わっているにも関わらず、”その能力を上手く発揮する(使う)ことができていない“という点です。
ですから、指導者の指導方針によって、”選手たちの能力が、いかに変化するか?“というのが、少しお分かりいただけたのではないでしょうか。
これはとても残念なことですが...
日本国内では、多くのジュニアサッカーの選手たちが、”その選手が持つ潜在能力を十分に発揮できないまま、大切なジュニア年代を過ごしている(過ごさせている?)“ように、私は個人的に感じてしまいます。
3. ポジションを意識したプレー ができる
私の長男も、幼児からサッカースクールを行っていたので、年代別でサッカーの内容が変化していく様子をこれまでに何度も目撃しています。
その中で特に顕著だったのが、”小学3年生から4年生にかけての時期“でした。
各々の選手たちが、相手選手たちやボールを観察しながら、”守るべきエリアや攻撃がしやすいポジションを意識したプレーができる“ようになっていきます。
たぶんこれは、
“脳および神経系の発達と密接な関係“
があるのだと思います。
なお、”脳の神経系の発達(脳神経可塑性)“に関する記事も過去に書かせていただいておりますので、更に理解を深めたい方は、下記の記事にも目を通しておいてください。
しかし、何故このように低学年から高学年に年代が変わっていくことで、これらの神経系が発達するのでしょうかね。
特に、”神経系の発達が向上する環境に置かれていた選手“というのは、”幼い年代からでもサッカーで活躍できる“ようです。
やはり、その中で参考になるのは”久保建英選手“ではないでしょうか。
それではここで、”久保建英選手の幼い頃からのプレー動画“を確認してみましょう。
(一部省略していますので、約1分40秒の動画です)
既に、彼は”2022年ワールドカップ・アジア2次予選にも召集“されることになっております。
先ほど紹介した動画を見ても分かるように、”相手ディフェンダーがどのような守備や動きをしてくるのかを事前に察知している“かのようにドリブルやプレーを選択(判断)しているのが印象的です。
また、彼のお父さんが書いた書籍(おれ、バルサに入る!)では、(当時、川崎フロンターレに所属していた頃の話)、”周囲の選手に自分から声をかけて、チーム全体がドリブル中心ではなく、パスも繋ぐようになるにはどうすれば良いか?“と親子で話し合ったことなどが書かれています。
こうした事実を知ると、”久保建英選手“は幼い頃から”ポジションを意識したプレーを頭で理解できていた“のだなと感じさせます。
何故、このように久保選手は”幼い頃から理解力があったのか?“と考えてみた時、それはやはり、脳神経可塑性を促す原動力にもなる”本人の行動がそうさせた“のではないでしょうか。
先ほどの動画の冒頭では、”どんな選手になりたい?“という質問に対して、当時まだ10歳であるにも関わらず、”まだこれからなので、少しずつ上にいけるようにしたいです“と答えています。
こうした発言から、
“久保選手の持っていた夢や目標が、かなり高いところにあった“
ことが伺えますね。
私も自身のサッカースクールで選手たちに、
“高い夢や目標を持つことで、それに必要な技能が身につけられる“
と伝えています。
ようするに、高い夢や目標を持つことで”本人の行動が変化する“わけですから、こうしたことを上手く活用していくことで、”選手たちの脳の神経系の発達も向上できる“ということになります。
その活動の中で選手たち自身が、
“どうすれば自分の夢や目標を達成することができるのか?“
と自問自答を繰り返しながら、少しずつ成長してくれればと願っています。
4. 戦術的な理解が高まる
確かに、サッカーの育成方針も重要です。
それでも、個々がそれぞれ夢や目標を持つことにより、”その為に何が必要か?“と自分の頭で考えるようになっていきますから、それに伴い”サッカーの戦術的な理解が高まる“ことが期待できます。
もし、”補欠のままでも別に構わない...“と考えているのであれば、”レギュラーになる為に必要なサッカーの戦術を学んで理解するという行動が減っていく“はずです。
逆に、久保選手のように”もっと上を目指したい!“と強く願っているのであれば、当然、それに見合った行動をしなければなりませんので、”サッカーの戦術を何が何でも理解するぞ!“と気持ちが変化していくはずです。
ただし、こうした強い気持ちが本人にあったとしても、それを学べるクラブやチーム、またはサッカースクール、それを指導する指導者が周囲に存在しなければ、”サッカーの戦術を学ぶという行動を起こすことができない“ということになってしまいます。
これはとても難しい問題です。
私自身も長男が幼い頃、本人がスラスラと読めて、かつ”簡単にサッカーの戦術が学べる良い本はないか?“と、色々と本を買い与えたことがあります。
しかし、なかなか幼い子供が理解できるような戦術の本が存在しません。
そうなってくると、本人の身近にいる”指導者や親御さんの存在“というものが大きくなっていくと思います。
いかにして、
“幼い子供の頭でも戦術が理解できるように説明することができるか?“
が重要になってくると思います。
私も、時々スクールに参加している選手たちに、戦術的なことを問いかけて、それに対する個々の考えを聞くことがあります。
つまり、ちょっとしたグループディスカッションのようなものですね。
ライフキネティックでは、このようにトレーナーが随時参加者に質問等をして、そのことについて参加者全員が共有し、”どのようにすることが有効なのか?“を共に考え、そしてそれらを解決していけるような時間を設けることがあります。
この辺については、トレーナーになる為の講習会において、マスタートレーナーからこれらの理論をしっかりと教わります。
なので、ただ闇雲にYouTube等でライフキネティックのエクササイズを見て真似ても、この運動プログラムの”効果は低い“ものになってしまいます。
現在では、日本サッカー協会においても、指導者ライセンスを取得する方に、ロジカルシンキングの存在を伝えていますが...
私の場合、”こうした理論に精通しない人たちが我々に壇上から説明し、どこまでそれらの内容を正確に伝えることができるのか?“と少し疑問を感じてしまったことがあります。
サッカーでは、
“他国や様々な理論の良い点だけ集めて、それを機能させるのは不可能“
です。
スペインサッカー、オランダサッカー、イタリアサッカー、ドイツサッカー等々...
“それぞれに特徴“があり、”祖国のサッカー指導者たちが長い年月をかけて築き上げてきた“ものです。
ですから、そんな選択をするのでなくて、”とてもシンプルなサッカーの基本戦術をしっかりと学んでいくことが重要“だと、私は個人的に考えます。
こうした観点を持ちながら、”高学年の練習メニューにおいて高い効果が期待できそう“なクラブやチームおよびサッカースクール、そして指導者を選択されると良いのではないでしょうか。
5.結果重視または内容重視で勝敗が左右する
ここまで記事を読み進めていくと、次第に”練習メニューの重要性“が理解できるようになってくると思います。
そして、その練習メニューや指導方針によって、選手たちのサッカーが”結果重視なのか内容重視なのか“も分かってくるはずです。
当然、それによって”試合の勝敗が左右される“ことも少なからずあります。
これは私個人の意見なので、
全てのジュニア年代に当てはまるわけではありませんが...
何となく、日本サッカー(特に育成年代)では、”指導者が在籍しているクラブやチームがある地域“で、”どこの地域よりも優秀な選手を育てようとしたがる“と感じます。
何故、そこまで地域にこだわる必要性があるのでしょうか?
私は、日本サッカー全体の事を考えて、より優秀な選手を育てて海外でも活躍してもらい、やがてその選手が日本代表選手となって、母国日本がワールドカップで優勝するのを見てみたいです。
もし、こんな夢が叶ったら、さぞや興奮することでしょうね!
では、皆さんのお子さんが所属するクラブやチーム、そして指導者たちは、選手たちの将来を第一に考えているでしょうか?
または、日本サッカーを底辺(ジュニア年代)から強化していこうと真剣に考えているでしょうか?
正直なところ、”結果重視のサッカー“では、「こうしたことを考える暇など無い!」というのが本音だと思います。
現在の日本では、レアルマドリードやバルセロナ、マンチェスターシティーにといった海外の強豪クラブに移籍するような選手が続々と育ってきています。
もし、日本国内の育成年代が、”内容重視でなく、結果重視だけのサッカー“であったならば、このような素晴らしい時代は訪れなかったかもしれません。
是非、今回の記事の内容を参考にしながら、”サッカーの低学年と高学年のトレーニング(練習)メニュー“というものを考えていただけたらと思います。
なお、”サッカーの育成“に関する記事も過去に書かせていただいておりますので、興味がある方は、是非こちらにも目を通してください。
まとめ
いかがだったでしょうか?
今回は、”少年サッカーの練習メニューについて“と、”低学年と高学年で知っておくべきポイント“を、ライフキネティック・トレーナーの視点からお伝えさせていただきました。
また、今回は”低学年と高学年で知っておくべきポイント“を5つずつ説明してみました。
こうすることで、”低学年と高学年には能力差がある“ということが理解できるようになるでしょうし、特に育成年代では、”どのようなトレーニングや練習メニューをする必要があるのか?“も少しずつ分かってくるのではないでしょうか。
個人的には、ここまで長く記事を書くつもりはありませんでしたが、自分なりに納得ができる内容で、しかも読む人が知りたい内容にすることを考えながら書いてみました(汗)
私の中では、サッカーとライフキネティック、そしてサッカーと脳神経可塑性が切っても切れない関係なので、初めて目にする方には少し読みにくさを感じたかもしれません(汗)
決して、短時間で記事を全て読み終えてくださいとは言いませんので、時間をかけながら、”ライフキネティックの有効性“や”脳神経可塑性“について理解を深めていただけたらと思います。
ここまでお読みくださり、ありがとうございました♪