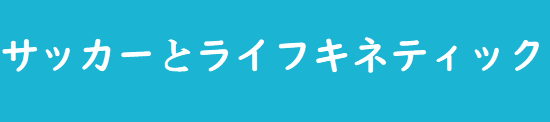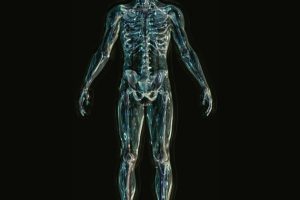今回は、”日本サッカーは弱い強いどちらなのか?“
そして、”海外の評価や反応“と”サッカーW杯の歴史から読み取れる技能“をお伝えしたいと思います。
この記事は、ライフキネティック・トレーナーの視点から書いていますので、他とは少し違った視点から分析しています。
そういう意味では、十分楽しめる内容になるのではないかと思います。
それでは本題に進みます。
目次
①ワールドカップの歴史と日本サッカー

まずは先に、”サッカーワールドカップの歴史“から触れていきたいと思います。
私たちが熱狂するサッカーの大会と言えば、4年に一度開催されるワールドカップですよね。
このワールドカップですが、いつから開催されていると思いますか?
表にして “簡単にまとめ” てみました。
| 開催年 | 決勝戦 | 3位決定戦 | ||
| 1930 | ウルグアイ① | アルゼンチン | アメリカ | ユーゴスラビア |
| 1934 | イタリア① | チェコスロバキア | ドイツ | オーストリア |
| 1938 | イタリア② | ハンガリー | ブラジル | スウェーデン |
| 1950 | ウルグアイ② | ブラジル | スウェーデン | スペイン |
| 1954 | 西ドイツ① | ハンガリー | オーストリア | ウルグアイ |
| 1958 | ブラジル① | スウェーデン | フランス | 西ドイツ |
| 1962 | ブラジル② | チェコスロバキア | チリ | ユーゴスラビア |
| 1966 | イングランド① | 西ドイツ | ポルトガル | ソビエト連邦 |
| 1970 | ブラジル③ | イタリア | 西ドイツ | ウルグアイ |
| 1974 | 西ドイツ② | オランダ | ポーランド | ブラジル |
| 1978 | アルゼンチン① | オランダ | ブラジル | イタリア |
| 1982 | イタリア③ | 西ドイツ | ポーランド | フランス |
| 1986 | アルゼンチン② | 西ドイツ | フランス | ベルギー |
| 1990 | 西ドイツ③ | アルゼンチン | イタリア | イングランド |
| 1994 | ブラジル④ | イタリア | スウェーデン | ブルガリア |
| 1998 | フランス① | ブラジル | クロアチア | オランダ |
| 2002 | ブラジル⑤ | ドイツ | トルコ | 韓国 |
| 2006 | イタリア④ | フランス | ドイツ | ポルトガル |
| 2010 | スペイン① | オランダ | ドイツ | ウルグアイ |
| 2014 | ドイツ④ | アルゼンチン | オランダ | ブラジル |
| 2018 | フランス② | クロアチア | ベルギー | イングランド |
第一回大会が1930年に開催されており、2018年までに21回開催ほどされています。(第二次世界大戦により、中断になった年もあります)
日本がワールドカップ本大会に初出場したのは、約20年前の1998年になってからです。(6大会連続出場:開催国出場枠1回)
こうしてサッカーW杯の歴史を振り返って見ると、
“世界大会における日本サッカーの歴史は浅い“
ことが分かると思います。
1位:ブラジル(5回)
2位:(西)ドイツ・イタリア(4回)
3位:ウルグアイ・アルゼンチン・フランス(2回)
4位:イングランド・スペイン(1回)
大会の半数をブラジル・ドイツ・イタリアが優勝しており、そこにウルグアイ・アルゼンチン・フランスが優勝2回で食い込み、イングランド・スペインが共に1回の優勝をしています。
このように見ると、アジア諸国がワールドカップで優勝する日なんてくるのかな...と少し不安になってきますよね。
なお、2002年の日韓開催で韓国が4位となっておりますが、この件については触れないでおきます。(色々と物議を巻き起こした部分なので)
こうした結果から、日本サッカーがワールドカップの決勝戦に進出する為には、これから先の開催で、準決勝戦まで進まなければ難しいことが分かります。
歴代の優勝国は、基本的に準決勝まで進んでいます。
例外として、クロアチアが前大会で決勝戦まで進みましたが、オーストリアやユーゴスラビアとも深く関わっているので、日本よりもサッカーの歴史は深いと思います。
日本が1998年に初出場した以前(1930年)から、サッカー強豪国は世界の表舞台でサッカーを競い合ってきています。
その差は、何と”70年近くある“わけです。
ちなみに、Wikipediaによると
1866年:横浜市でイギリス軍が行った試合が初という説
1872年:神戸市の外国人居留地で行われた試合が初という説
1874年:現在の東京大学工学部のスコットランド人(測量技師)が体育教育の一環としてサッカーを教えた説
少し飛んで
1954年:FIFAワールドカップ・地区予選で初めて日本がW杯に参加
色々と説はあるようですが、だいたい1866~1874年の間にサッカーが日本に持ち込まれ、アジア予選に初めて参加したのが1954年です。
その間、”1998年まで一度も本大会出場はしていない“のです。
ただし、オリンピック競技の方では、それなりの結果を出しましたが、あえてここでは取り上げません。(出場枠が明らかに少ないので参考になりません)
これだけ、サッカー強豪国との歴史に差があると、”サッカーの技術や能力“や”指導方法“にも”大きな差が出てくるはず“です。
では、その辺のことを次のコーナーからお伝えしていきたいと思います。
②日本サッカーは弱い強い?

ということで、そんな”日本サッカーは弱い?強い?“どっちなの?
ハッキリと言ってしまうと、
“決して弱くはない“です。
ただし、大きな世界大会等で、優勝や3位までに入賞するほどの力は残念ながら持っていません。(ここでは女子サッカーを除いています)
何故、大きな世界大会で良い成績を残せないのか?
それは、
“予選突破自体が非常に難しい“
からです。
サッカー強豪国でさえ、大きな世界大会で予選敗退を喫してしまいます。
つまりこれは、余程の実力差が無ければ、本大会で準決勝や決勝戦まで進むことができないということを意味しています。
当然、育成年代の指導が成功しているかどうかも大きなカギを握っています。
そう考えると、サッカー強豪国からすれば、”日本サッカーはさほど強くない“ということになってしまいますが...
では、”海外の評価や反応“はどうでしょうか?
1.海外の評価や反応
では、日本サッカーに対する”海外の評価や反応“はどうでしょうか?
現在、”開催中のコパアメリカ“で日本は、連覇を狙う”チリ代表を相手に0-4と大差“をつけられたものの、第2戦の”ウルグアイ戦では何とか維持を見せて2-2と善戦“することができました。
しかも、出場している日本代表選手の多くは、”オリンピック代表を中心とした若いメンバーで構成“されています!
次戦、”第3戦となるエクアドル代表との試合結果“によっては、”予選リーグ突破も十分有り得る“でしょう。
ただし、日本で開催されるキリンカップ(招待試合)とは違い、完全なるアウェー(敵地で戦っている)状態で試合をしているので”立場としてはかなり厳しい状況“と言えます。
しかし、第2戦終了後にウルグアイ代表の選手たちから、”日本代表の素早い動きに苦戦した“というコメントも残されており、今後こうした部分を活かすことができれば、”サッカー強豪国と十分に戦える“と言えるかもしれません。
2.海外から評価されている選手
この大会で”海外から高く評価されている選手“ですが、既に皆さんもご存知だと思いますが、現在、話題急上昇中の “久保建英選手” です。
彼は、”育成年代をスペインのバルセロナ“で過ごしていた時期があり、”かなり高いレベルで戦えることを世界に証明“することができています。
そうしたこともあり、コパアメリカでの試合直前に、育成時代を過ごしたバルセロナではなく、ライバルクラブとなる”レアルマドリードへの移籍“が報道されました。
バルセロナで育ったのに、我々としてはとても残念ですよね。
下記の本を読んでいたので尚更です...
彼の持ち味は、
何と言っても “状況判断の高さ” です。
こうした能力があるからこそ、代表クラスの高いレベルでも冷静に状況を判断して、シュート・ドリブル・パス・ボールキープを”瞬時に選択することができている“ようです。
“久保建英選手の動画“も紹介しておきます。
(一部省略していますので、約20秒の動画です)
実は、この動画でもやっている
“ボールの受け方に秘密“
があります。
この”バルセロナで培われた技術“がここで活かされているわけですね!
こちらの技術に関しては、
後のコーナーでお伝えしたいと思いますので、是非お楽しみに♪
その他、日本代表で”海外から評価が高い選手“と言えば...
“中島翔哉選手“ですね。
彼は幼い頃、”2つのサッカースクール“に通いながら、”フットサル教室も利用していた“という話があります。
彼の主な経歴を書き出してみます。
2004年(当時10歳)ヴェルディの下部組織へ入団
2011年(当時17歳)U-17日本代表選出。U-17ワールドカップ出場
2012年(当時18歳)トップチームに2種登録選手として帯同
2014年(当時20歳)FC東京に完全移籍(カターレ富山へ期限付き移籍)
2014年(リーグ半ば)FC東京に復帰
2016年(22歳)U23代表選出。オリンピック本大会出場
2017年(当時23歳)ポルトガル1部ポルティモネンセ移籍
2019年(現在24歳)カタール1部アル・ドゥハイルSC
彼の持ち味は、左サイドからのカットインです。
(一部省略していますので、約15秒の動画です)
彼の”持ち味はドリブル“ですが、それによって孤立してしまう場面も多少出てくることがあります。
この辺が日本サッカーにとって、上手くシステム化されていない部分なのではないでしょうか。
サッカー強豪国には、必ずと言って良いほど、世界で活躍しているアタッカーが複数存在しており、その選手を試合の中で活かせるかどうかで、”勝敗が決まることも決して珍しくない“です。
今後の日本サッカーの課題としては、
“いかにドリブラーをシステム上で機能させるか?“
にあるのではないでしょうか。
また、”天性のドリブラー(素質を持った選手)“は、大人になってから誕生するものではありません。
そうした選手を
“育成年代で発掘” または “育てていく環境“
も必要ですよね。
③世界との技術および能力差

先ほど、久保建英選手のコーナーで触れましたが、ここでは”世界との技術や能力差“について触れてみたいと思います。
ところで皆さんは、
どんな部分に”世界との技術差や能力差“を感じていますか?
私は、
“ワールドカップの歴史と深い関係があるのではないか?“
と推測しています。
冒頭でもお伝えしたように、サッカーのワールドカップは1930年から開催されているわけで、日本サッカーが初めてそれに参加したのは1954年と”約20年以上もの差がある“ことが分かります。
更に、本大会初出場が1998年ですから、本大会出場以降の経験で言うと、”約70年以上もの差がついている“わけです。
この差を皆さんは、どのように判断しますか?
もうちょっと頑張れば追いつく?
それとも、あと数年もすれば追いつく?
または、まだまだ数十年はかかりそう?
こんな予想をしても何も始まりませんが...
“世界が使っている技術や能力“に目を向ければ、自ずと”解決策が見えてくる“のではないないでしょうか。
そこで私が注目したのが”古武道“です。
何やら怪しげな雰囲気ですが、”日本のサッカーの歴史が浅い“のであれば、逆に”日本古来から存在する歴史が深いもの“を取り入れるべきだと思うのです。
これならサッカーの歴史が浅い日本でも、サッカー強豪国の技術や能力と互角に戦えると思えませんか?
そのヒントは
“古武術の垂直離陸“
にあります。
この技術や能力をサッカーで使うことができれば、様々なサッカーの技術や能力をアップさせることができると思います。
どのような技術や能力かというと...
参考までに”イブラヒモビッチのゴールシーン“を紹介します。
(一部省略していますので、約10秒の動画です)
皆さんも動画をご覧になったと思いますが、この時のイブラヒモビッチは”左足で力強く地面を蹴る“とか”地面を踏ん張る“ことをしていません。
サッと右足の膝を抜いて、素早く右方向へ移動しているだけです。
(他にもお伝えできない要素が幾つかあります)
これだけの巨体を素早く横移動させる技術と能力...
世界トップレベルの選手は本当に凄いですよね!
サッカー強豪国の選手たちは、これらの技術や能力を”サッカーという歴史の中から習得“しています。
これでは、
“サッカーの歴史の深い国が有利になる“
のは目に見えています。
ならば我々も、
“歴史の深いもので勝負すれば良い“
と思いませんか?
日本では、法令や政令で国技を定めていないようですが、
“大相撲(アマチュア相撲)”
“柔道”
“剣道”
“弓道”
こうしたものが、
“宮内庁から天皇杯を下賜(かし)されている武道“
だと言われています。
では、サッカー強豪国の国技はどうでしょうか?
1.サッカー強豪国の国技
では日本以外の”サッカー強豪国の国技“を見ていきましょう。
- ブラジル
カポエイラ(ブラジルの奴隷達が練習していた格闘技?) - ドイツ・イタリア・イングランド・ポルトガル
サッカー - アルゼンチン
パト(ポロとバスケットの要素を組み合わせたゲーム?)
このように見てみると、サッカーに深く関わる国技が多少なりとも感じ取れると思います。
やはり、イタリアとドイツの国技はサッカーでしたね。
だからサッカーも強いはずです(汗)
2.日本古来の武道で強豪国に勝つ!
そこで私は、先ほどから紹介している”日本古来の武道で強豪国に勝つ!“ことができるのではないかと考えています。
では、動画で紹介した”イブラヒモビッチのゴールシーン“をご覧になっているという流れで、再度この部分に触れていきたいと思います。
サッカー強豪国の選手たちに見られる技術やコーディネーションの中には、”不思議と日本古来の武道に共通した部分“が見られます。
ちなみに、私は初めから武道に興味を持ったのではなく、世界トップレベルの選手たちを見ていた際、”日本古来の武道と共通点がある“と感じ取り、それらに興味を持ち始めたことが始まりです。
当然、サッカーと共通する動きをしているのですから、それらに興味を持ってしまいますよね。(特に、私のような人間は)
では、その技能をバルセロナの動画で見てみましょう。
(一部省略していますので、約10秒の動画です)
特に、メッシがボールを受けながらトラップをする場面などは、”古武術の垂直離陸“と非常に似ているように感じませんか?
前回の記事でも書きましたが、
“古武術の三方切りの動き“
と非常に酷似していると思います。
このように、イブラヒモビッチ(スウェーデン)といい、バルセロナ(スペイン)といい、歴史の深い強豪国のサッカーには、技術とコーディネーションの秘訣がたくさん組み込まれています。
特にスペインでは、ボールを受ける際の動きに、それぞれ固有の名称があるそうです。
3.コントロール・オリエンタード
私は、スペインのサッカーに関しては詳しくありません。
ですが...
そんな私でも、”コントロール・オリエンタード“というサッカーの技能に関しては、凄く興味を持っています。
でもここでは、
あえて私よりも詳しい人や詳しいサイトを紹介することにします♪
先ほど紹介した”古武術の垂直離陸と酷似“している”スペインのボールの受け方“を詳しく解説しているサイトや動画がありましたので、それをご紹介したいと思います。
【COACH UNITED(参考サイト)】
スペインで徹底されるジュニア年代が身につけておくべきスキル
(https://coachunited.jp/column/000840.html)
なお、このコントロール・オリエンタードというボールの受け方は、”おれ、バルサに入る“でも紹介されています。
こんなことは、
“全国レベルの高校サッカー部なら誰でも知っている“
ことだと思います。
ただ、”皆さんが知らないだけ“なのです。
ですから私が参考にするのは、
“説明の仕方の部分“になります。
指導者として、とても参考になる説明だと思います♪
言い方や教え方は違えど、
“中身が一緒なら問題ない“
ですよね?
多くの人は、
“サッカー強豪国の中に、サッカーの全てが含まれている“
と思いがちです。
これは断言しますが、絶対に違います。
日本にも”同じような技術やコーディネーションが存在する“のです!
それを多くの人に少しでも知っていただけらたらと思います♪
まとめ
いかがだったでしょうか?
今回は、”日本サッカーは弱い?強い?“から始まり、”海外の評価や反応“、そして”ワールドカップの歴史から見たサッカーの技能“についてお伝えしました。
スペインには、サッカーの長い歴史があり、それぞれの動きなどに名称があるということが分かりましたよね。
でも、ここは日本なので、そんなものは必要ありません(笑)
それぞれ”オリジナルの名称を用いれば良い“だけです。
私の開催するライフキネティック・サッカースクールでは、それぞれの指示に対してオリジナルの名称を付けて、それに則した動きやコーディネーションを選手たちがしています。
言い方は違えど、言葉や状況で判断するという部分では何ら変わりありません。
何故なら、全ての情報は”目“や”耳“から入り、
それを”脳が処理する“からです。
つまり、”そこまでサッカー強豪国の技術やコーディネーションに強くこだわる必要性はない“ということです。
その技術やコーディネーションの存在を知っている指導者に教われば良いだけの話です。
日本古来の武道をヒントに、
“海外の評価や反応を日本サッカーは強い!“
に変えていきましょう!
ここまでお読みくださり、ありがとうございました♪