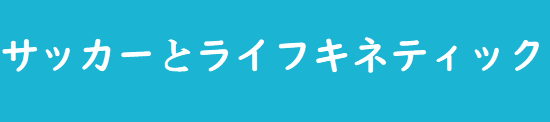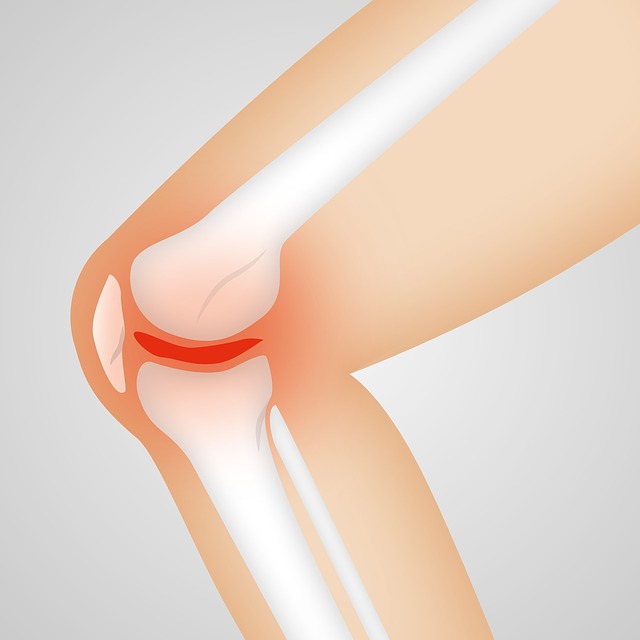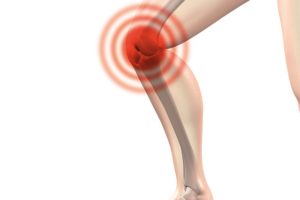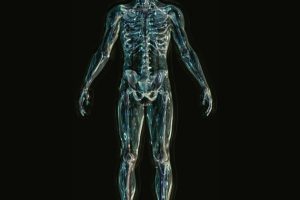今回は、”サッカーの膝抜き(LSD)“に加えて、”古武術にある井桁理論“も踏まえながら、”そのコツとやり方“ついてお伝えさせていただきます。
こちらの記事は、以前お伝えした下記の記事の続きとなります。
前回の記事で説明した”LSD(Long・Slow・Distance)“を日々継続し、”サッカーで有利になる為の膝抜き“を身体に沁み込ませることに成功すると、次第に”新たな感覚“が得られるようになります。
これは”自身でやってみないと絶対に得られない感覚“です。
そして、ここから先のことは、あくまでも”私自身が実際に行って得た感覚“として皆さんにお伝えしていきます。
まずは、”膝抜きの感覚が得られる“ようになると、徐々に”骨盤や肩の動きに対して以前よりも敏感になる“はずです。
これを古武術でいうと、
身体の崩しの部分で”井桁理論“にあたります。
どのような理論なのかは、次のコーナーから説明します。
目次
①膝抜きと井桁理論
では、”膝抜きと井桁理論“についてお伝えします。
まずは、参考動画がYouTubeにもあったので参考までにご覧ください。
(一部省略していますので、約60秒の動画です)
次にこちらは、”古武術を実践している甲野善紀氏の動画“です。
(一部省略していますので、約25秒の動画です)
前者の膝抜き発進は、”地面に足を長く接地させる”ことで、”地面からの反発を得るという内容“となっています。
後者のナンバ歩きは、”身体のうねりを発生させない”ことで、”より効率的な身体操作が可能になるという内容”となっています。
どちらが優れているかは判断することが難しいですが...
個人的には、
“地面反射または反力や伸張反射と深く関係している“ように思います。
②井桁理論のコツとやり方

では、”井桁理論のコツとやり方“ですが、私のイメージとしては”操り人形が一番に連想“されます。
これは、”糸で宙吊りにされた人形を操るもの“です。
このイメージと感覚を持てるようになると、”人間の骨格を意識した骨盤や肩の動き“が今までよりも理解しやすくなります。
これは、よく私が
“指導する選手たちに説明していたイメージとコツ“です。

上記の画像のようなアルミ缶を
“片側だけ押し潰す“とどうなるでしょうか?
まずは、これを選手たちにイメージさせます。
一般的な同じイメージを持てる選手なら、この時に”押し潰した逆側の中央部分が破裂または膨らむというイメージを持つ“はずです。
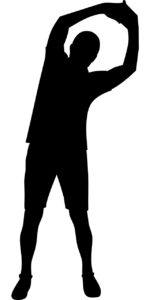
これを人間の身体でイメージすると、
上記の画像のように”押し潰した側の肩と骨盤が近くなり(縮む)、逆側の肩と骨盤が遠くなる(伸びる)という動きになるはず“です。
こうしたイメージや感覚を持つことで、”サッカーにおける井桁理論“というものが少しずつ理解できるようになっていきます。
では、これらを”サッカーに応用した井桁理論のやり方“について、ここで少し触れておきます。

この画像のように、こちらから向かって”右側の肩と骨盤が近くなる(縮む)”ことで、左方向への推進力を得る“というのが”井桁理論を最も簡単に説明または理解できる方法“ではないかと思います。
他にも”意識すべき細かい点“が幾つかあります。
先ほどのコーナーで少し触れましたが、
“筋肉の伸張反射“や”地面からの反射や反力“なども意識します。
こうした”人体にかかる物理的な法則も意識“しながら取り組んでいくと、”より素早く左右への動き出しが可能“になっていきます。
③井桁理論の先に見えたもの

ここでは、”井桁理論を理解していくことで、その先に見えたもの“についてお伝えします。。
その見えたものですが...
“伸ばすや縮める“といった身体の動きに深く関係している”胴体力“という身体操作です。
ですから私の取り入れた流れとしては...
二軸動作 → 古武術 → 胴体力
このように、当初は”二軸動作“から興味を持つことになり、そして”古武術で得た膝抜きと井桁理論“によって、”人の身体操作というものを追求“していことになりました。
この”井桁理論の先に見えた胴体力“では、”ただ単に伸ばす縮めるといった動きだけではない“です。
当然、その時の”軸の置き方や感覚を感じ“ながら”身体に問いかける作業が主“になります。
ですから、”小さなお子さんには難しい作業“と言わざるを得ません。
でも、”こうした身体操作を幼い頃から身につけさせていきたいと考える“のが、指導者の考えでもあり、強い欲求でもあります。
そして、これら様々な身体操作を知った上で、自身なりに作り上げてきた各種トレーニングが、”現在ムービーレッスンで提供している内容“となっています。
私の中には、”子供は頭で理解するよりも、その動きを見て真似て感覚として記憶していった方が効率が良い“という考えがあります。
そして、これを育成年代の子供たちに”より効率的に習得“させていく為に、”ライフキネティックを取り入れた“というのが最大の狙いです。
このライフキネティックを取り入れたことで、身体の動きを中心(先)に考えるのではなく、脳を中心(先)に考え、”あくまでも脳からの指令として身体を素早く機能させる“という考え方に変化していくことになりました。
※ムービーレッスンにおいて、”ライフキネティックに関するエクササイズの提供はしておりません“ので、予めご了承ください。
このムービーレッスンの”利用登録ID数には限り“があります。
まだまだ誰もが自由に学べるツールにはなっておりませんが、少しずつ窓口を広げ、より多くの方に各種トレーニングを提供していけたらと考えております。
まとめ
いかがだったでしょうか?
今回は、”サッカーの膝抜き(LSD)“に加えて、”古武術にある井桁理論“も踏まえながら、”そのコツとやり方“ついてお伝えさせていただきました。
ジュニア年代では、こうした内容を理解することが難しいですが、ジュニアユース(中学生)年代になると、徐々にこうした内容を理解できるようになっていきます。
当然、こうした活動を地道に続けて、”補欠からレギュラーになった選手を何人も育てきた“という経験が私にはあります。
最後に、これは繰り返しになりますが重要なことなので、もう一度お伝えさせていただきます。
“人がやらないようなことを継続するのが努力“であり、”それをするもしないも本人の行動力と向上心次第“ということです。
本当に、”このサイドの記事や内容を理解できている人“ならば、”今から、または明日から何かしら行動に移すはず“です。
そうすることで、”脳が変化(脳神経可塑性)“し、それに伴って”身体も変化(自由に動かせるようになる)“していきます。
その為の記事も幾つか書いておりますので、下記の記事も是非ご覧になってみてください。
ここまでお読みくださり、ありがとうございました♪